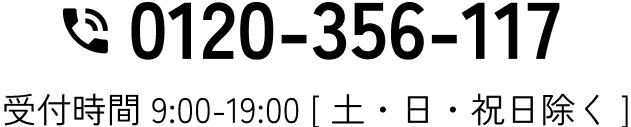other
何でも屋で起業する際に必要な資金・手続き・資格と年収とは
少子高齢化と共働きの増加により、何でも屋の需要が増えている傾向があります。また、何でも屋は「初期費用を抑えて開業できる業種に見える」という理由で参入する場合があります。
何でも屋を開業するには、車両購入費まで含めれば250万円程度、フランチャイズに加入する場合は300万円程度の費用がかかります。店舗型の開業では1,000万円以上の費用がかかることがあるため、資金がなくても開業できるわけではありません。
この記事では、何でも屋の開業に必要な資金、手続き、資格を解説します。何でも屋や便利屋の開業を考えている人は、参考にしてみてください。
いくらの資金調達ができる?
無料診断 電話で無料相談
【受付】平日9:00~19:00
何でも屋の業務内容は幅広い
何でも屋は便利屋とも言われ、基本的には、依頼主が自分ではできない事、やってもらえると嬉しいという軽作業を提供します。
【何でも屋の主な業務内容】
- 片付け
- 清掃
- 不要品処理
- 代行
- 送迎
業務内容はあくまで一例であり、様々なサービスを提供している場合があります。何でも屋を開業予定の人は、目安にしてみてください。
①家の片付けをする
何でも屋は、依頼者の代わりに家具の修理・組み立て・取り付け・家事の手伝いなどを行う場合があります。
②清掃・庭の掃除・害虫駆除をする
何でも屋は、ハウスクリーニングとしてエアコンの清掃、ガスコンロの油やコゲの除去、水回りの汚れの清掃などを行う場合があります。また、ゴキブリ・ダニ・ノミ・クモ・シロアリなどの害虫駆除や庭の草むしりと草の処分も行う場合があります。
③不要品処理をする
何でも屋は、引っ越しの際に、処分しにくい大型家具や家電などの不用品処分を行う場合があります。また、何でも屋は遺品処分を行う場合もあります。
④代行をする
何でも屋は、依頼人の代わりに日用品や食料品などの買い物を代行する場合があります。また、ペットシッターの依頼を受け、散歩の代行を行う場合もあります。
⑤病院・学校・習い事への送迎
何でも屋は、病院への送迎や学校・保育園・習い事などの送迎を行う場合があります。
フランチャイズに加盟して何でも屋を開業する場合もある
フランチャイズの何でも屋は、運営会社(本部)が研修でノウハウを教えてくれ、必要な資材やユニホームやホームページを用意してくれます。
加盟するフランチャイズによりますが、がホームセンターやリフォーム会社などと提携している場合があるため、安定して仕事を受注できることもあります。
ただし、オーナーとして何でも屋の会社と契約する際には、加盟金や保証金などの初期費用が必要です。
また、オーナー契約をして何でも屋を開業したあとは、毎月本部にロイヤリティを支払い続けなければいけません。ロイヤリティの内訳はフランチャイズの運営会社により異なりますが、商標使用料やサポート費用が含まれます。
何でも屋の開業に必要な資格はある?
何でも屋を開業する時点では、必要な資格は特にありません。個人事業主として開業する場合は、開業後1か月以内に事業所(自宅など)を管轄する税務署に開業届という書類を提出します。
ただし、何でも屋は前述した通り、幅広いサービスを提供する場合があります。そのため、何でも屋としてどのような仕事を請け負うかによっては、以下のような資格が必要になります。
|
あなたが行う業務 |
何でも屋で必要となる資格の名称(取得する場所) |
|
不用品を引き取って販売する |
古物商許可 (事業所を管轄する警察署経由で都道府県の公安委員会) |
|
依頼主を車両に載せて運転する |
普通2種運転免許(運転試験場で技能試験を受ける) |
|
コンセントの交換など電気工事に関わる仕事を請け負う |
電気工事士(第一種、第二種)、(全国各地・インターネット受験) |
|
一般家庭のごみなどの廃棄物を処分するために処理場まで運ぶ |
産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県知事または政令市長から許可) |
|
ペットシッターの仕事を請け負う |
第一種動物取扱業の「保管」登録(自治体における保健所) |
個人でこれらの資格をゼロからすべて取っていくのはお金も時間もかかる場合があります。必要に応じ、既にこれらの資格を持つ事業者と連携することも視野に入れましょう。
何でも屋で必要になる開業資金
①個人で開業する場合は250万程度かかる
個人で何でも屋を開業する場合、主に車の購入費用がかかります。運搬車両をすでに持っているケースは開業資金を抑えられる可能性がありますが、清掃用具を運べるだけの運搬車両を購入し、当面の運転資金を準備する場合には250万円程度が必要となります。
当サイトでは、金融機関から融資を受けられるか、また開業の状況によって使える補助金は無いかなど、資金調達に関する無料診断ができます。開業資金を自己資金のみでまかなうのが難しい場合など、いくらくらいの資金調達ができそうか気になる人は、無料診断を試してみてください。
いくらの資金調達ができる?
無料診断 電話で無料相談
【受付】平日9:00~19:00
(1)車の費用で100万円
何でも屋をするには、軽トラックなどの運搬車両が必要です。店舗は必要ありません。自宅を店舗として、電話も固定電話ではなく携帯電話で受注できます。
(2)宣伝広告費で50万円
何でも屋のサービスを始めるには、お客さんにあなたのビジネスを知ってもらうための宣伝ツールであるチラシとホームページと名刺が必要です。チラシとホームページ作成で50万円程度はみておきましょう。
無料でできる宣伝としては、ツイッターやFacebookなどのSNSがあり、地道に毎日続ければ効果も見込める場合があります。
(3)道具と作業費で10万円
提供するサービス次第では工具や清掃用具が必要となります。道具一式と作業着を揃える資金として10万円程度は必要です。
(4)車両維持費(毎月1万円)と通信費(毎月1万円)で毎月2万円
車のガソリン代や保険代や税金、そして依頼主と連絡するための通信費として毎月2万円程度はかかります。ハウスクリーニングを請け負う場合は、保険を車だけでなく、ハウスクリーニング保険(年間で7~8万円)にはいっておくことも検討しましょう。
(5)開業後の生活費も用意しておく
何でも屋は集客が課題になる場合があるため、開業後しても生活ができるように半年分程度の生活費を用意しておきましょう。
②フランチャイズで開業する場合は300万円程度が必要
フランチャイズに加盟すると、必要な道具やホームページをフランチャイズ本部が用意してくれることがあります。そのため、フランチャイズに加盟する際は250万円、研修だけを受ける場合は100万円程度で何でも屋を開業できる場合があります。
関連記事
この記事の監修者

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
開業に関するお悩みサポートします!
- 資金調達と財務計画を立てることが難しい
- どうやって効果的に顧客を獲得するかが分からない
- 法的な手続きや規制が必要であり、それらに対するリテラシーがない
- 開業に必要な特定のスキルや知識が不足していると感じる
開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、
事業用融資の資金調達をはじめ、創業者支援をメインとする会社です。
私たちが確かなサポートと専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。
開業に関するご相談はこちら
無料相談